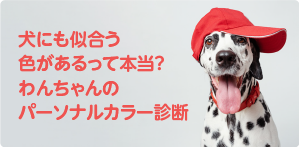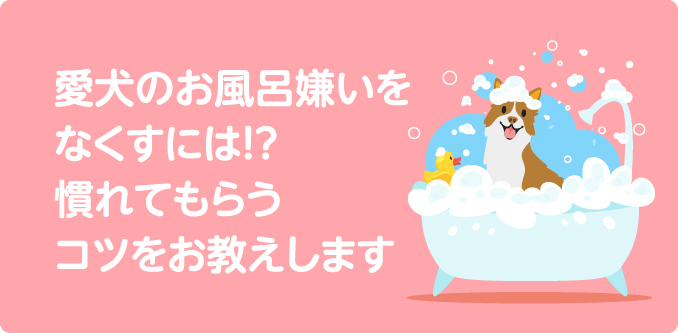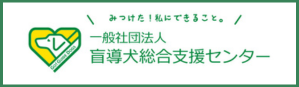家猫でも油断大敵!ノミ・ダニから愛猫を守る予防と対策法
目次
「愛猫が最近よく掻いていたり、皮膚にプツプツとしたできものがあったりしませんか?」愛猫の皮膚にこのような症状がある場合は、ノミやダニに感染している可能性があります。
何もせずに放置すると、強いかゆみや貧血の症状が現れることがあり、元気をなくしたり食欲が低下したりする場合もあります。
この記事では、『愛猫には毎日快適に過ごしてほしい!』と願う飼い主さんに向けて、猫に害をもたらすノミやマダニに感染した場合の症状や効果的な予防法、治療法をご紹介します。
※一般的に『ダニ』と認識しているのは、室内に生息する『チリダニ』ですが、猫に大きな害をもたらすのは、屋外に生息する『マダニ』です。この記事では、『マダニ』を『ダニ』として表記しています。
1.室内猫でも安心できない!ノミ・ダニを放置するとどんな症状が出る?
 猫を室内で飼っている場合、ノミやダニの感染は関係ないと思っていませんか?
猫を室内で飼っている場合、ノミやダニの感染は関係ないと思っていませんか?
実は、室内猫であってもノミやダニに感染することがあります。感染すると、かゆみを中心とした辛い症状が出るだけでなく、飼い主さんや同居動物にも皮膚症状が現れることがあるので注意が必要です。
近年、マダニが媒介する病気として人にも重篤な症状を引き起こす『重症熱性血小板減少症(SFTS)』への関心が高まっています。
『重症熱性血小板減少症(SFTS)』は、下痢や嘔吐といった消化器症状や発熱症状を示し、重篤な場合には命を落とすこともある怖い病気です。
ノミ・ダニによる感染は、特に子猫やノミ・ダニ予防をしていない猫、基礎疾患を抱えている猫などに症状が重くなる傾向がありますので、特に配慮が必要です。
それでは、猫がノミやダニに感染した場合に見られる症状の一例をご紹介します。
猫たちの健康を守るためにも、ぜひ知っておきましょう。
①かゆみやブツブツなどの皮膚炎
猫がノミに感染すると、非常に強いかゆみを感じることが多い一方で、ダニに感染した場合は、かゆみがほとんどないか、軽度にとどまるケースが多く見られます。
皮膚には赤みや『丘疹(きゅうしん)』と呼ばれる小さなブツブツ、脱毛やかさぶたなどの症状が見られることもあります。
特に猫では『粟粒性皮膚炎(ぞくりゅうせいひふえん)』と呼ばれる、主に背中や頭部に粟粒状(ぞくりゅうじょう)の小さな丘疹が多数現れることがほとんどです。
猫にこのような症状が現れた場合は、身体の不調を訴えている可能性があるので、早めに気づいてあげるようにしましょう。
②アレルギー症状
一部の猫は、ノミやダニが吸血する際に分泌する唾液にアレルギー反応を起こすことがあります。本来、ネコノミは宿主の猫にアレルギーを引き起こしにくいとされています。
そのため、多くの猫では、ノミに刺されても軽いかゆみや小さな発疹ができる程度で自然治癒することがほとんどです。
しかし、ノミやダニの唾液に対して敏感な体質の猫は、アレルギー反応を起こし、非常に強いかゆみが見られることがあります。
その結果、強いかゆみのために皮膚の浅い部分がただれる『好酸球性局面(こうさんきゅうせいきょくめん)』や、皮膚の深い部分に及ぶただれ『無痛性潰瘍(むつうせいかいよう)』といった症状が見られる場合もあります。
③貧血や削痩、下痢や発熱など
ノミ・ダニの感染が重度の場合は、猫が痩せたり、貧血の症状が見られることがあります。また、瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)という寄生虫を持つノミを飲み込んだ場合や、ヘモプラズマという寄生虫に感染した猫の血を吸ったダニに刺された場合には、下痢や発熱といった症状が現れることがあります。
日本ではあまり見られませんが、「急性のダニ麻痺」という状態になることがあります。
これは、マダニが注入した神経毒によって、猫がふらつく、歩行困難になるといった神経症状が引き起こされるケースです。
愛猫の健康を守るためには、日頃からノミやダニの予防を徹底し、異変を感じたら早めに獣医師に相談しましょう。早期の対応が何よりも大切です。
2.家猫がノミ・ダニに感染する経路とは?
「家の中だから安全」と思いがちですが、家猫もノミ・ダニに感染する可能性があります。感染経路としては、主に以下の3つがあります。
①人を介した感染
 飼い主さんが外出した際に、衣類や靴にノミ・ダニが付着し、知らないうちに家の中に持ち込んでしまうことがあります。特に、猫を飼っているお宅に訪問した時や、動物病院、ペットカフェなど猫に関連した場所へ行った際には注意が必要です。
飼い主さんが外出した際に、衣類や靴にノミ・ダニが付着し、知らないうちに家の中に持ち込んでしまうことがあります。特に、猫を飼っているお宅に訪問した時や、動物病院、ペットカフェなど猫に関連した場所へ行った際には注意が必要です。
愛猫をノミ・ダニから守るためには、帰宅後に衣類を軽く払ったり、玄関マットで泥を落としてから家の中に入るなど、ちょっとした工夫をすることが大切です。
猫にとっても、飼い主さんにとっても安心できる環境を保ちましょう。
②ベランダや窓からの侵入
 ノミやダニは、ベランダや窓、家の小さな隙間からも侵入してくることがあります。猫が少しだけベランダや庭先に出るだけでも、ノミやダニに感染するリスクは十分にあります。
ノミやダニは、ベランダや窓、家の小さな隙間からも侵入してくることがあります。猫が少しだけベランダや庭先に出るだけでも、ノミやダニに感染するリスクは十分にあります。
ノミやダニの感染リスクを抑えるために、ベランダや窓に網戸を設置したり、防虫対策をしっかり行い愛猫が安全に過ごせる環境を整えてあげましょう。
③他の動物との接触
 猫の他に、散歩に行く犬を飼っている場合や、外猫と触れ合う機会がある場合は、ノミやダニが家猫に感染することがあります。愛猫を守るためには、こうした接触機会にも注意が必要です。
猫の他に、散歩に行く犬を飼っている場合や、外猫と触れ合う機会がある場合は、ノミやダニが家猫に感染することがあります。愛猫を守るためには、こうした接触機会にも注意が必要です。
また、ノミ・ダニは、野良猫だけでなく、アライグマやネズミといった多くの野生動物にも寄生していますので、これらの動物が敷地内に侵入する可能性がある場合には、飼い主さんがしっかりと対策を取ることが大切です。
愛猫が安心して暮らせる環境を守るために、敷地内の点検や野生動物との接触を避ける工夫を心がけましょう。
3.家猫のためのノミ・ダニ対策!おすすめの予防法の種類
愛猫の健康を守るために、ノミ・ダニの予防はとても大切です。ノミ・ダニの予防薬はホームセンターなどでも購入できますが、できるだけ動物病院で処方してもらうのが安心です。
なぜならば、市販薬だと猫の体質に合わない場合があるからです。動物病院で処方したものは万が一トラブルが発生しても主治医が適切に対応することができます。
また、予防は月に1回の頻度で行い、年間を通して継続して行うようにしましょう。
もし、年間で予防が難しい場合は、特にノミ・ダニが活発になる4~11月くらいの暖かい時期だけでも行うことがおすすめです。
以下に予防薬に関する種類を3つそれぞれご紹介します。
飲み薬タイプ
最近では、ノミ・ダニ予防に飲み薬を使用することが主流になりつつあります。飲み薬は予防の効果が高く、手軽に実践できるため確実な予防法として人気です。
薬を飲むのが苦手な猫の場合は、愛猫がリラックスしている入眠のタイミングや、ボーっとしているタイミングを見計らって投薬しましょう。もし投与後すぐに吐いてしまい、吐いた物の中に薬が見える場合は、もう一度投与することを検討しましょう。
ただし、投与してから時間が経過している場合は、すでに吸収されている可能性もあるため、無理に再投与せず、そのまま様子を見てあげるといいでしょう。
滴下タイプ
滴下タイプは、飲み薬タイプに比べると手頃な価格のものが多く、多くの飼い主さんに利用されています。この方法は、猫が舐めて取ることができない肩甲骨の間に、数か所に分けて丁寧に塗布するのがポイントです。
ただし、長毛種や被毛が密集している猫の場合は、薬が皮膚ではなく被毛に付いてしまい、期待する効果が得られない可能性があります。
その場合は、塗布したい箇所の一部を毛刈りしてから塗布するか、飲み薬への変更を検討するといいでしょう。
また、猫の皮膚は外用薬に敏感なことが多いため、薬によっては皮膚炎を起こすことがあります。
塗布後に赤みやかゆみの症状が出ていないか、皮膚状態をしっかりチェックしてあげるようにしましょう。
ブラッシングや無理のない入浴も予防になる
 日頃からのブラッシングは、スキンシップの時間にもなり、愛猫の体調を早く察知するためにもとても大切です。
日頃からのブラッシングは、スキンシップの時間にもなり、愛猫の体調を早く察知するためにもとても大切です。
ブラッシング中に、黒褐色のノミフンや吸血中のマダニ、動き回るノミを見つけることがありますので、注意深く観察してみましょう。
また、入浴が苦手ではない愛猫であれば、お風呂で物理的にノミ・ダニを洗い流すのも効果的な方法です。
ただし、無理にお風呂に入れようとすると、猫がストレスを感じてしまったり、体調を崩してしまうため、入浴が嫌いな猫の場合は、無理せず他の方法を選んであげましょう。
愛猫の健康を守るためには、無理のない範囲で予防を続けることが大切です。猫にとって、できる限りストレスがない方法で予防をするようにしましょう。
4.家猫を守るために今日からできること:予防と早期発見がカギ!
愛猫の健康を守るためには、ノミ・ダニの予防がとても大切です。
ノミ・ダニ感染は、かゆみやアレルギー症状を引き起こし、猫にとっては大きなストレスになってしまいます。そのため、まだノミ・ダニの予防をしていない場合は、早めに動物病院で猫に合ったお薬を処方してもらいましょう。
また、愛猫が快適に過ごせるように、部屋を清潔に保つことも重要です。さらに、猫とのスキンシップを兼ねたブラッシングを定期的に行うことで、体調の変化を早く察知することができます。
愛猫が安心して暮らせる環境を作り、予防と早期発見に努めるようにしましょう!
Instagramでもペットに関する情報を発信中!フォローお待ちしております。
▼Instagram
https://www.instagram.com/petpo_petlife/
▼その他猫に関するおすすめ記事はこちら
猫がかきむしりをする理由や対処法とは?
猫の抜け毛は病気?抜け毛の多くなる理由とおうちでできる対策
愛猫が太りすぎ?猫の肥満対策と健康長寿を目指すためのダイエット方法
飼い方・おでかけ, 飼い方・おでかけ